まさか、娘が不登校になるなんて。
これが私の最初のキモチでした。「不登校」という言葉は知っていても、まさか娘が… 最初は現実を受け入れられず、不安と戸惑いの中で、何とかしなきゃと必死に動きました。
でも、不登校の初期対応って想像以上にしんどい。
 わたし
わたし子どもが学校へ行かない不安、怖さ、悲しみそんな気持ちは同じ経験をした方にしかわかりません。「つらいね、わかるよ」って声をかけてくれる方の子どもは不登校ではないんだもの……
この記事では、私の実体験をもとに不登校の初期対応のつらさと向き合う視点をお伝えします。同じように悩む親御さんの参考になりますように…
・元不登校の息子と不登校の娘のお母さん
・不登校をきっかけに家族関係を見直す
・息子現在留学生活を満喫中
・娘心の土台をコツコツ建設中
・不登校で闇の中にいる親御さんに「大丈夫!」を伝えたい
・どん底にいた私が今に至るまでの不登校のあれこれを発信中
・詳しいプロフィールはこちらから
不登校の初期対応は親にとってつらいもの|その理由と乗り越え方


「娘はどうなっちゃうんだろう?」
それが、不登校の始まりに私の頭をよぎった最初の言葉でした。
- 勉強についていけなくなる
- 友達が離れていって孤立してしまう
- 将来、社会に出られなくなる
- ゲームばかりする生活になって昼夜逆転する
「私が死んだら、この子はどうやって生きていくの?」
次から次へと、最悪の未来ばかりを想像してしまうのです。それはきっと、不登校の「初期対応」をがんばっている親御さんなら、誰しも一度は通る心の道ではないでしょうか。
不登校は、ある日突然やってくるように見えて、実は少しずつ積み重なった“しんどさ”の結果だったりします。けれど、親にとっては予期せぬ出来事。「まさかうちの子が……」という思いが、パニックと不安を何倍にも膨らませてしまうのです。
最初のうちは、どう動けばいいのかまったくわかりませんでした。
無理にでも学校に行かせるべき?
それとも休ませるべき?
どこに相談すればいい?
どう話しかけたらいい?
夫にも申し訳ない。両親にも言えない。ママ友とも会いたくない。誰にも会いたくない、何も考えたくない、できることなら引っ越してしまいたい――。
「不登校の初期対応」は、まるでこの世の終わりのような心境になることさえあります。
そんなとき、どうか自分を責めないでください。あなたが今、つらいと感じているのは当然です。わが子のことを思うからこそ、先の見えない不安や焦りが押し寄せてくるのです。
この時期、親は「何とかしなきゃ」と必死になります。けれど、実は子どもも同じくらい――いえ、それ以上に苦しんでいるのかもしれません。だからこそ、親の心が少しでも落ち着くことが、子どもにとっての「安心」にもつながります。
不登校の初期対応に疲れたとき、やってほしい3つのこと


娘の不登校が始まって間もない頃、私は「できることは何でもしてあげよう」と思っていました。
担任の先生と連絡を取り、子どもが安心できる選択肢を探し、ネットで情報を集め、体調を気づかい、声をかけ… とにかく「良かれと思って」動き続けました。
けれど、あるときふと気づいたのです。こんなに頑張っているのに娘は何も変わらない。そして、私はどんどん疲れていく。娘との距離も、どんどん遠くなっていくと。
思えば、無理をしていたんだと思います。
娘の友達が「遊ぼう」と手紙をくれるのは、ありがたいけれどつらかった。ママ友が「何かあったら言ってね」とメールをくれても、助けは求められなかった。気づけば誰からも声がかからなくなっていました。
娘も、外に出るのを嫌がるようになり、私も、学校という場所から少しずつ距離を置くようになりました。まるで「静かな逃避」のように、親子でコミュニティから離れていったのです。
不登校の初期対応に必死になるあまり、心も身体もすり減ってしまうことがあります。それでも親は、「私が頑張らなきゃ」と思ってしまいがちです。けれど、親が疲れ切っていると、子どもは安心できません。
不登校の子どもは、とても繊細です。親が張り詰めていると、その空気を敏感に感じ取ります。だからこそ、子どものSOSに寄り添うには、まず親自身のケアが大切なのです。
まずは、次の3つのことを試してみてください。
①気持ちを正直に話せる相手とつながる
②1日10分でも自分のための時間をつくる
③子どもと「何もしない時間」を過ごす
「いい対応をしなきゃ」「正しいやり方を探さなきゃ」と追い込むより、まずはあなた自身の「今の気持ち」に目を向けてみてくださいね。
親が安心していないと、子どもも安心できません。逆にいえば、親がホッとすることが、子どもの回復につながる第一歩になります。
不登校の初期対応で大切な見守り方とは?親が注意したいポイント


子どもが不登校になると「まずは見守りましょう」って言われませんでしたか?私はこの言葉に戸惑いました。
見守るってどういうこと?何もしないってこと? 口を出さず、ただ静かに待つこと?それとも、心の中で祈ること?
そんな曖昧な言葉に、私は混乱しました。娘が苦しんでいるのに、私は何をすればいいのか。
「母親が変われば子どもも変わる」
「お母さんが自分の人生を楽しんで」
そんな言葉さえ、当時の私には受け入れられませんでした。
だって、私の何がいけなかったのかわからなかったから。娘が不登校になって「好きなことを楽しんで」なんて言われても…
毎日が手探りで、私は「何が正しいのか」ばかりを探し続けていました。一方で、現実の娘はどんどん変わっていきます。
朝起きるのが難しくなり、夜は私と同じベッドでしか眠れなくなりました。日中も私から離れようとせず、どこに行くにもついてくる。その状況が、私は正直つらかったのです。
「受け入れなきゃ」「娘の方がしんどいんだ」と思えば思うほど、自分の苦しさにフタをして、どんどん心がすり減っていきました。
不登校の初期対応は、本当に苦しい。地獄のような日々でした。
そもそも、私の子ども時代には「学校に行かない」という選択肢なんてありませんでした。もちろん、イヤなこともあったけど、それでも学校は「行くもの」だったし、何だかんだ言いながら、友達と笑って帰ってきた日々の記憶があります。
だから、娘の不登校が理解できなかったんです。
でも、「見守る」という言葉の本当の意味は、「子どもの不安を否定せず、隣にいてあげること」だったのかもしれません。
何かを変えようとしなくていい。「元気にさせなきゃ」「学校に戻さなきゃ」と焦らなくていい。ただ、今日もここにいてくれる。それだけで、子どもは少しずつ安心していくのかもしれません。
もちろん、それが簡単じゃないことは、身をもって知っています。ずっと一緒にいるのはしんどいし、何も解決していないような焦りに押しつぶされそうになる。
それでも、「今のわが子をありのまま受け止める」ことからしか、回復の一歩は始まらないのだと思います。
「見守る」ことは、何もしないのではなく、「あえて何もしすぎない」勇気なのかもしれません。
不登校の初期対応に限界を感じたとき|親がたどり着いた気づきとは


「見守るしかない」そう思って、言いたい言葉を飲み込んで、ただ隣にいようと努力しても、心の中では葛藤が渦巻いていました。
だんだん何も感じたくなくなって、ある日、ふっとこう思ったのです。
「もう、落ちるところまで落ちてしまおう」
自分でも驚くような思考でした。不登校の初期対応で心が限界を迎えたとき、気持ちがジェットコースターのように乱高下します。
「これでいい」と思えたかと思えば、次の瞬間には「このままではダメ」と自分を責めてしまう。
ある朝、急に手が震えました。涙が止まらなくなって、息が浅くなって。けれど、病院に行く気力もない。家を出ることすらできない。だから、とにかく何かをしていないと、自分を保てなかった。
やたらと掃除をしたり、クローゼットを片づけたり、家中のいらないものを処分したり。手を動かしているときだけが、少しだけ無になれる気がしました。
でも、頭の中は「不登校」でいっぱいなんです。



この先、娘はどうなるんだろう…
学校に戻れる日は来るのかな?
今のこの状態が一生続いたらどうしよう…
建て直そうとすればするほど、逆に気持ちは崩れていきました。
不登校の初期対応が「見守り」だと言われても、見守るどころか、自分が壊れていくような感覚。これは、誰にも見せられない地獄です。
でも今振り返ると、落ちるところまで落ちたからこそ、初めて見えたものがある気がします。
「もう、どうにでもなれ」と諦めた私。そして、その諦めが、ある意味回復の入り口だったのかもしれません。
最後に|不登校の初期対応に悩む親が回復を感じ始めた瞬間


落ちるところまで落ちて、もう何もできない、何もしない… そうやって諦めた瞬間。私は、心のどこかで「何かを手放す準備」ができたのかもしれません。
手放すもの、それは娘を変えようとする気持ち。良かれと思って押しつけていた「こうあるべき」の正解。そして「母親としてちゃんとしなきゃ」という自分へのプレッシャー。
あるとき、専門家の方がこう教えてくれました。
「たとえ親子でも、価値観は違うんですよ」
「子どもは“血のつながった他人”だと思ってみてください」
この言葉が、スッと胸に入ってきました。
それまで私は無意識に、「お母さんはこう思ってるんだから、あなたも同じでしょ?」と、娘に共感を強いていたんだと思います。
でも娘は私とは違う人間。不安の感じ方も、疲れたときの反応も、まったく違う。
私は「自分の価値観の型」に、娘を無理に当てはめようとしていました。それが、どれほど娘を苦しめていたか… ようやく気づくことができました。
もしかしたら、あなたも私と同じように「わかってほしい」「気づいてほしい」とお子さんに思っているかもしれません。
「私の気持ちに、なんで応えてくれないの?」
「どうしてあなたはそんなに自分勝手なの?」
そう問いかけたくなる気持ち、痛いほどわかります。でも、子どもは「わかってくれない親」にはさらに心を閉ざしていってしまうんですよね。
私たち親がまずできることは、「子どもを変えようとしないこと」なのかもしれません。それに気づいたとき、私は少しずつ回復し始めました。娘との関係も、ほんの少しだけ柔らかくなった気がします。
落ちるところまで落ちたときこそ、気づけることがあります。諦めたように見えても、実は「手放した」だけ。そこには、きっと回復への小さな道がつながっています。
今、まさに不登校の初期対応で悩んでいる方にぜひ読んでいただきたい本があります。この本は、子どもの気持ちを理解し「自分とは違う存在」として受け止めるヒントが詰まった本です。ぜひ、読んでみてくださいね。
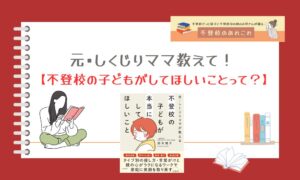
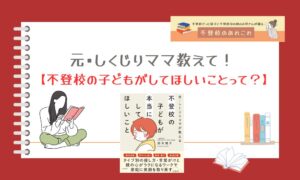
不登校でお悩みの親御さんへ
子どもが学校に行けなくなるのは、単なる反抗や甘えではありません。「こうするべき」「親の期待に応えなければ」と無意識に抱え込んでいた心の重さが、限界を越えてあふれ出た結果です。
親だからできることすりも、「人として寄り添う」ほうが、子どもにとっては何よりの安心になるはずです。あなたとあなたのお子さんにも、心から安心できる時間が訪れますように。
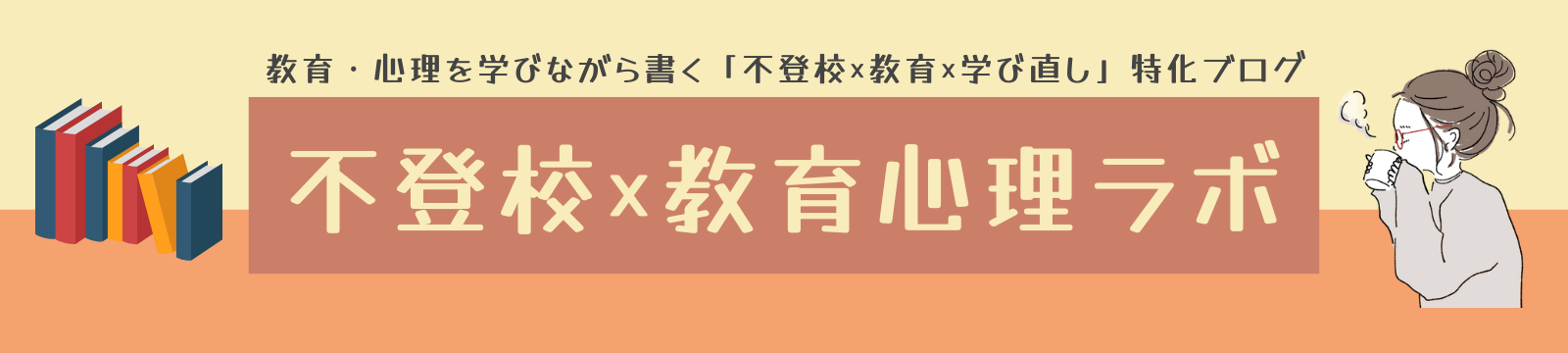
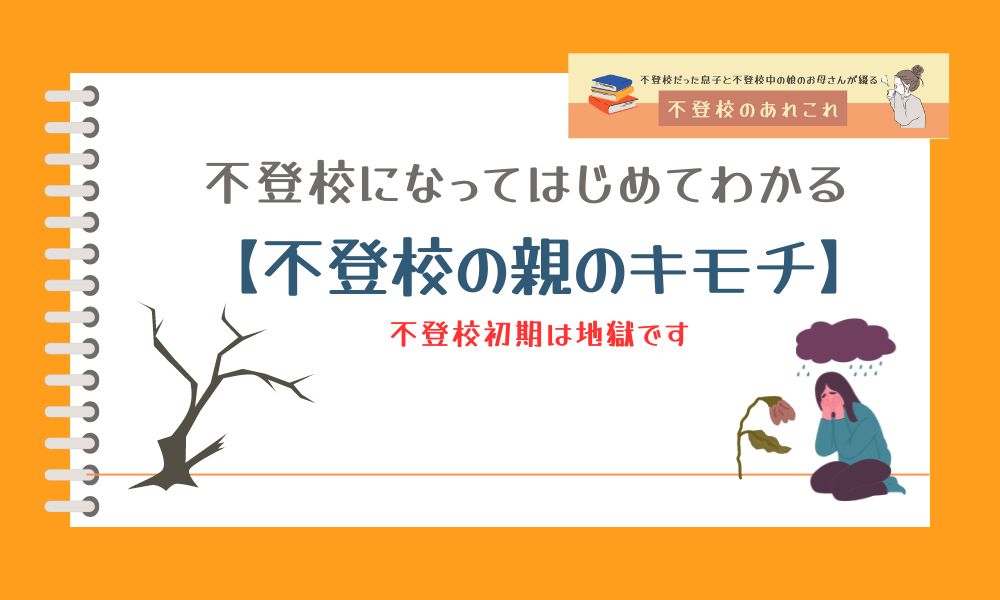
コメント