「まさか、うちの子が不登校になるなんて…」
厳しい中学受験を乗り越え、憧れの中高一貫校に合格したお子さんが、ある日突然「学校に行きたくない」と言い出したら、親として動揺するのは当然です。
実は、中高一貫校の不登校は決して珍しいことではありません。
文部科学省の調査によると、中学校の不登校率は年々増加傾向にあり、特に学習プレッシャーの強い進学校では、優秀なお子さんほど心の負担を抱えやすいという現実があります。
「このまま退学させるべき?」
「何とか卒業まで支えられない?」
「転校という選択肢もあるの?」
そんな不安と迷いの中にいる親御さんに向けて、同じ経験をした親である私が進路の選択肢についてお伝えします。
 わたし
わたし子どもの人生なのに、ついつい「親の立場」で正解探しをしてしまうんですよね。私も本当に悩みました。
どの道を選んでも、必ず光は見えてきます。ぜひ、参考にしてくださいね。
・元不登校の息子と不登校の娘のお母さん
・不登校をきっかけに家族関係を見直す
・息子現在留学生活を満喫中
・娘心の土台をコツコツ建設中
・不登校で闇の中にいる親御さんに「大丈夫!」を伝えたい
・どん底にいた私が今に至るまでの不登校のあれこれを発信中
・詳しいプロフィールはこちらから
中高一貫校で不登校で不登校になる原因とは?
中高一貫校は、高い学力と豊かな人間性を育む教育環境として多くの親御さんから支持されています。しかし、親御さんの立場からみると恵まれた環境のように思える学校も、お子さんにとってはつらい場所になってしまうケースもあります。
「こんなはずじゃなかった」と、入学してから現実とのギャップに苦しみ、不登校になるお子さんも少なくありません。ここでは、中高一貫校における不登校の背景と、お子さんが直面する可能性がある課題についてくわしく解説します。
中高一貫校の教育システムが生む特有のストレス
中高一貫校の最大の特徴は、6年間の一貫したカリキュラムです。この長期的な視点に立った教育プログラムには、以下の特徴があります。
| 特色 | 内容 |
|---|---|
| 系統的な学習 | ・中学1年生から高校3年生まで6年間を見据えた計画的な学習が可能 ・基礎から応用まで段階的に理解を深められる |
| 受験ストレスの軽減 | ・高校受験がない ・受験勉強に追われず、じっくりと学習に取り組める |
| 発展的な教育 | ・通常の中学・高校よりも進んだ内容を学べる ・知的好奇心を刺激する機会が豊富 |
| 豊富な校外活動 | ・修学旅行や文化祭など6年間を通じて多彩な行事や活動がある |
このように、中高一貫校の教育システムは親目線で見ると本当に素晴らしいですし、お子さんに合えば最高の環境で6年間を過ごせます。



高校受験がないので思い切り部活に打ち込めるなどのメリットもあり、中高一貫校の受験を決めるご家庭も多いかもしれませんね。
しかし、中高一貫校ならではの環境は、お子さんに大きなストレスを与える場合があります。ストレスの要因としては、以下が挙げられるでしょう。
- 高い学力レベルの維持:
入学時から高い学力が求められ、常にそのレベルを保つ必要があります。 - 長期的な競争:
6年間同じ環境で過ごすため、長期的な競争ストレスにさらされます。 - 進路の早期決定プレッシャー:
早い段階から大学進学や将来の進路について考える機会があり、プレッシャーを感じます。 - 部活動や課外活動の負担:
多くの中高一貫校では、学習面だけでなく部活動や課外活動にも力を入れています。
これらの活動が、お子さんにとって過度な負担になるケースもあります。
このようなストレスに耐えきれないお子さんは、不登校になるリスクが高くなる恐れがあります。
不登校になりやすい生徒の特徴6つ
中高一貫校で不登校になりやすいお子さんには、以下のような特徴が多くみられます。
- 完璧主義傾向:
高い目標を掲げすぎて、それを達成できないと強いストレスを感じます。 - コミュニケーションの苦手意識:
クラスメイトや教師とのコミュニケーションに困難を感じ、学校に行くこと自体に不安を覚えます。 - 学力の伸び悩み:
入学時は高い学力を持っていても、周囲についていけず自信を失います。 - 興味関心の変化:
中学入学時に抱いていた目標や興味が、成長とともに変化し、学校生活とのミスマッチを感じます。 - 過度な期待へのプレッシャー:
親や教師からの高い期待に応えようとするあまり、精神的に追い詰められます。 - 自己肯定感の低下:
常に高い水準を求められる環境で、自分の価値を見出せなくなります。
これらの特徴は、決してお子さんの欠点ではありません。むしろ、敏感で真面目な性格のお子さんほど、中高一貫校に適応するのが難しいケースもあるのです。
中高一貫校の不登校 | 早期発見のサインと初期対応
中高一貫校での不登校は、お子さんと親御さんの両方にとって大きな試練です。しかし、適切な対応とサポートがあれば、困難な状況も乗り越えられるでしょう。
ここからは、中高一貫校に通うお子さまの不登校の兆候を早期に発見し、効果的に対応する方法をくわしく解説します。
見逃さないで!不登校の前兆チェックリスト
多くの親御さんは、お子さんが学校へ行けなくなってから「学校で何かあったのかな?」とお子さんの様子に注意を払います。「もしかしたら、いじめられるかも」などの不安が頭をよぎる親御さんもいるでしょう。
しかし、不登校は、突然始まるのではありません。多くの場合、お子さんに何かしらの変化が現れる兆候があります。
以下のチェックリストで、お子さんの様子を振り返ってみてください。ただし、これらの兆候に1つでも当てはまったからといって焦る必要はありません。
成長過程での一時的な変化の可能性もあります。チェックリストを参考に適切なタイミングでサポートしていただけたらと思います。
また、お子さんを監視したり責めたりするためのチェックリストではありません。
早期サポートのために活用してくださいね。チェックリストは専門家の判断に変わるものではないので、心配な場合は必ず専門機関に相談してください。
【身体症状チェック】体に現れるサイン
□ 朝起きられない日が増えた
- 以前はすんなり起きていたのに、起こしても起きない
- 休日は普通に起きられるのに、平日だけ起きられない
□ 頭痛・腹痛・吐き気を頻繁に訴える
- 「お腹が痛い」「頭が痛い」と朝によく言う
- 病院で検査しても特に異常が見つからない
□ 学校に行く直前に体調不良になる
- 家を出る時間になると急に具合が悪くなる
- 午前中の体調不良が多く、午後には回復している
【学校関連チェック】学校への態度の変化
□ 学校や先生、クラスメイトの話を避ける
- 「今日学校どうだった?」と聞いても「別に」「普通」しか言わない
- 以前は学校の話をよくしていたのに、最近は話したがらない
□ 宿題や学校の準備をしなくなった
- 宿題を忘れることが増えた
- 制服に着替えたり朝の準備を嫌がる
□ 学校行事への参加を嫌がる
- 運動会や文化祭などを楽しみにしなくなった
- 「行きたくない」「面倒くさい」とよく言う
【生活リズムチェック】日常生活の変化
□ 夜更かしが増えて生活リズムが乱れた
- 以前より遅く寝るようになった
- 夜中にスマホやゲームをしている時間が長い
□ 食事の量や時間が不規則になった
- 朝食を食べたがらない
- 好きだった食べ物に興味を示さない
□ 起床時間がどんどん遅くなっている
- 平日も休日のように遅く起きる
- 朝の準備に時間がかかるようになった
【感情・行動チェック】心の変化のサイン
□ 些細なことでイライラしたり落ち込んだりする
- 以前なら気にしなかったことで怒る
- 急に泣き出したり、感情の起伏が激しい
□ 家族との会話が減った
- 家族と一緒にいる時間を避ける
- 話しかけても返事が短い、または無視する
□ 自分の部屋に閉じこもりがちになった
- リビングにいる時間が明らかに減った
- 部屋から出てこない時間が長い
【学習・成績チェック】勉強面での変化
□ 得意だった科目の成績が急に下がった
- これまで良かった科目で点数が取れなくなった
- テストの点数に一喜一憂しなくなった
□ 課題の提出を避けるようになった
- 宿題や課題を「忘れた」と言うことが増えた
- 提出物の準備を後回しにする
□ 勉強に対する意欲がなくなった
- 「勉強しても意味がない」などの発言が増えた
- 以前は自分から勉強していたのに、今はまったくしない
【友人関係チェック】交友関係の変化
□ 学校の友達との連絡が減った
- 以前はよく友達と電話やメールをしていたのに最近はない
- 友達から連絡が来ても返事をしたがらない
□ 休日に外出を嫌がるようになった
- 友達と遊ぶ約束をしなくなった
- 「みんなで遊ぼう」と誘われても断ることが多い
□ 友達の話をしなくなった
- 以前は友達の話をよくしていたのに、最近は一切話さない
- 友達に関する質問を嫌がる
【部活・趣味チェック】興味関心の変化
□ 熱心だった部活動に興味を示さなくなった
- 部活の話をしなくなった
- 部活を休みがちになった、または「やめたい」と言い出した
□ 好きだった趣味や活動への関心がなくなった
- 以前夢中になっていたことに興味を示さない
- 「つまらない」「やりたくない」と言うことが増えた
□ 新しいことに挑戦する意欲がなくなった
- 「どうせ無理」「やっても意味がない」と最初から諦める
- チャレンジ精神が明らかに低下している
親がができる初期対応
中高一貫校に通うお子さんの不登校の兆候に気づいたら、親御さんは以下の対応を心がけましょう。親御さんが勉強の遅れを気にするあまり、お子さんを無理に学校へ行かせようとするのは逆効果です。
不登校の長期化を防ぐためにも、初期対応は焦らず丁寧に取り組まなければなりません。
| 対応 | 方法 |
|---|---|
| 傾聴と共感 | ・話をじっくり聴き、感情を受け止める ・批判や叱責を避け、気持ちに寄り添う |
| 安心感の提供 | ・「どんな状況でもあなたの味方だよ」というメッセージを伝える ・無条件の愛情を示し、家庭を安心安全な場所にする |
| 原因の特定 | ・学校生活のどの部分に困難を感じているか具体的に聞く ・いじめや学業ストレスなど、潜在的な問題がないか観察する |
| 生活リズムの維持 | ・規則正しい食事と睡眠のリズムを保つ ・可能であれば、起床時間と就寝時間を保つ |
| 段階的なアプローチ | ・無理に登校させない ・別室登校など柔軟な対応を学校と相談する |
| 興味関心の維持 | ・好きなことや得意なことを一緒に楽しむ時間を作る ・学校以外の場所で、新しい経験や学びの機会を探す |
| 家族の協力 | ・家族全員でサポートする ・兄弟姉妹にも状況を説明する |
| 専門家への相談 | ・必要に応じて心療内科などの専門家に相談する ・早い段階でのカウンセリングが問題の長期化を防ぐ場合もある |
これらの対応は、必ずしもすべてのお子さんに当てはまるものではありません。大切なのは、親御さんが適切な見守りをできるかどうかです。



親の不安や心配を押し付けて、学校へ行けないお子さんを責めたり否定したりしないようにしてくださいね。
スクールカウンセラーとの効果的な連携
スクールカウンセラーは、不登校問題に対する専門的な支援を提供する重要な存在です。学校内に配置されているため、お子さんの学校生活の詳細を把握しやすく適切なアドバイスが期待できます。
スクールカウンセラーは、お子さんの心理状態や不登校の背景を専門的に分析し、適切な支援を提案してくれます。定期的に面談して話を聞いてもらううちに、お子さんの心の負担が軽くなるケースもあるでしょう。
相談内容は守秘義務により保護されるので、安心して相談できます。
中高一貫校での不登校対応策
不登校の児童生徒は、年々増加の傾向です。厳しい中学受験を乗り越えて合格を勝ち取った中高一貫校においても、残念ながら何らかの理由で不登校になってしまうお子さんもいるのです。
では、お子さんが不登校になってしまったらどのような対応策があるのでしょうか。ここでは、効果的な不登校対応策についてくわしく解説します。
学校側の支援体制を最大限に活用する
中高一貫校では、不登校に対するさまざまな支援体制を整えています。多くの学校では別室登校できる環境を整えるなど、お子さんの状況に応じた柔軟な対応が可能です。
また、ICTを活用した遠隔授業も増えており、自宅にいながら授業に参加できる環境を整備している学校もあります。
学校内では、担任、養護教諭、スクールカウンセラーなど、複数の教職員が連携してお子さんをサポートしてくれるでしょう。親御さんと支援の方向性を確認し、お子さんの状況や変化をみながら支援体制を整えます。
不登校のお子さんに対する支援体制は、学校によって異なります。お子さんが不登校になった場合は、最適な支援を受けられるように学校側と十分なコミュニケーションを取るように心がけましょう。
カウンセリングを効果的に活用する
多くの中高一貫校には、スクールカウンセラーが常駐しています。スクールカウンセラーは、学校環境をよく理解しており、お子さんの心理的な課題に対処できるでしょう。
学校のカウンセリング体制だけでは不十分な場合、外部の心理カウンセリング機関や医療機関を検討するのもいいかもしれません。ただし、即効性を求めすぎずに、じっくりと時間をかけて取り組む姿勢が大切です。
カウンセリングを効果的に活用するためには、定期的に通いカウンセラーとの信頼関係の構築が重要です。
【進路選択】中高一貫校から退学・転校する場合
中高一貫校での不登校が長期化し、改善が難しいと判断した場合、退学・転校を検討するケースがあります。中高一貫校からの退学・転校は、お子さんにとっても親御さんにとっても大きな決断です。
しかし、退学・転校がお子さんにとって新たな出発点となる可能性もあるでしょう。
ここでは、中高一貫校から退学・転校する際のそれぞれのメリット・デメリットについてくわしく解説します。
私立中学校への転校
私立中学校への転校は、中高一貫校と似た環境を維持しながら新たな場所で学ぶ機会を得られる選択肢です。
| デメリット | |
|---|---|
| ・中高一貫校と同様に高度な教育プログラムを提供 | ・公立に比べて学費が高額 ・家計への負担が大きくなる |
| ・公立中学に比べてきめ細かな指導を受けられる | ・転入試験がストレスになる |
| ・お子さんの興味や適性に合った学校を選びやすい | ・人間関係や学習環境の構築に時間がかかる |
| ・施設や設備が充実 ・さまざまな学習や活動の機会がある | ・転校前の学校と大きな変化はない ・不登校が続く可能性がある |
私立中学校への転校を検討する際は、お子さんの学力レベルや興味、将来の進路希望などを考慮して最適な学校を選ぶのが重要です。また、転校後のサポート体制についても事前に確認しておくとよいでしょう。
公立中学校への転校
公立中学校への転校は、新たな環境で学ぶ機会を得られると同時に、地域社会とのつながりを深められる選択肢です。
| ・授業料が無料 ・教育にかかる費用を大幅に抑えられる | ・中高一貫校と比べて授業の内容や進度が異なる |
| ・地元の同じ年齢の子どもと共に学べる ・地域社会との結びつきが強くなる | ・個別のケアが受けにくい |
| ・さまざまな背景を持つ子どもが集まる ・多様な価値観に触れる機会が増える | ・設備や教材が中高一貫校ほど充実していない |
| ・高校受験を通じて進学の道が開かれる | ・転校前の学校との差を感じる ・適応できない可能性がある |
公立中学校への転校を検討する際は、学区の確認や学校の特色、不登校生徒への対応などの下調べが大切です。また、転校後も継続的なサポートが受けられるよう、学校側と十分なコミュニケーションを取るようにしましょう。



我が家の息子は、退学して公立中学へ転校しました。プレッシャーから解き放たれ、友人にも恵まれ、みるみる表情が明るくなりました。
フリースクールという選択肢
フリースクールは、従来の学校システムとは異なるアプローチで教育を提供する場所です。不登校のお子さんにとっては、新たな学びの場となる可能性があります。
| デメリット | |
|---|---|
| ・お子さんの興味や学習スタイルにあった場所で学べる | ・正式な学校として認められていない ・卒業資格が得られない |
| ・少人数できめ細かなサポートを受けられる | ・経済的負担が大きい |
| ・競争的な環境から離れられストレスが軽減する | ・進学や就職の際に不利になる可能性がある |
| ・体験学習や芸術活動などがある ・さまざまな経験を通じて成長する機会が得られる | ・教育方針を周囲から理解されない場合がある |
フリースクールに通う場合は、通信制高校に在籍するなどして高校卒業資格を取得できるように検討するのもいいでしょう。
中高一貫校の卒業を目指す場合の復学戦略
中高一貫校での不登校は、親御さんにとって予想外の事態かもしれません。親御さんの気持ちとしては、中学受験して合格した学校を卒業して欲しいと思うのは当然でしょう。
たとえ、お子さんが不登校になったとしても、お子さんの状況に応じた適切なアプローチで退学を回避できる可能性もあります。
段階的に復学を計画
中高一貫校で不登校になってしまうと、復学は簡単ではありません。お子さんの学校へ行く意欲が戻ったからといって、保護者様が前のめりになり復学を急かしてしまうのは逆効果です。
お子さんのペースを尊重しながら、段階的に進めていかなければなりません。
- まずは家庭で学習リズムを作り、無理のない範囲で学習を進める
- 定期的にスクールカウンセラーと面談し、学校と連携する
- 短時間登校から始めるなど、徐々に学校で過ごす時間を延ばしていく
- 教室以外の場所で授業を受ける別室登校を検討する
- お子さんの状態を見ながら、教室での授業参加を少しずつ増やす
このように、お子さんの気持ちに寄り添いながらステップを踏んで復学を目指しましょう。
サポート体制の構築
お子さんの復学を支えるには、学校、家庭、専門家の連携したサポート体制が不可欠です。担任やスクールカウンセラーと面談し、学習面でのサポート方法や配慮事項について相談しておきましょう。
家庭においては、安心して過ごせる居場所づくりと、規則正しい生活リズムを心がけましょう。お子さんの学びのモチベーションを維持する工夫も必要です。
また、保護者様はお子さんの不登校の背景にある問題を理解して、不登校の再発防止に努めましょう。
最後に | 中高一貫校で不登校になっても大丈夫!
中高一貫校での不登校は、お子さんと親御さんにとって大きな試練です。しかし、退学、転校、卒業のいずれを選択しても大丈夫!どの道を選んでも、お子さんは自分で自分の未来を切り拓いていきます。
ですから、親御さんが悲観する必要はありません。
大切なのは、お子さんの気持ちに寄り添い、適切にサポートすることです。不登校の経験を通じて、お子さんの自己理解が深まり、より強く、しなやかな人間に成長する可能性があります。
お子さんの個性や能力を再発見し、新たな可能性を開く転機となるかもしれませんよ。



何が正解かは渦中にいるとわからないものです。困難な選択ではあるものの、お子さんと一緒に悩み最終的に決めた決断は、のちに間違いではなかったと思える日が来るはずです。
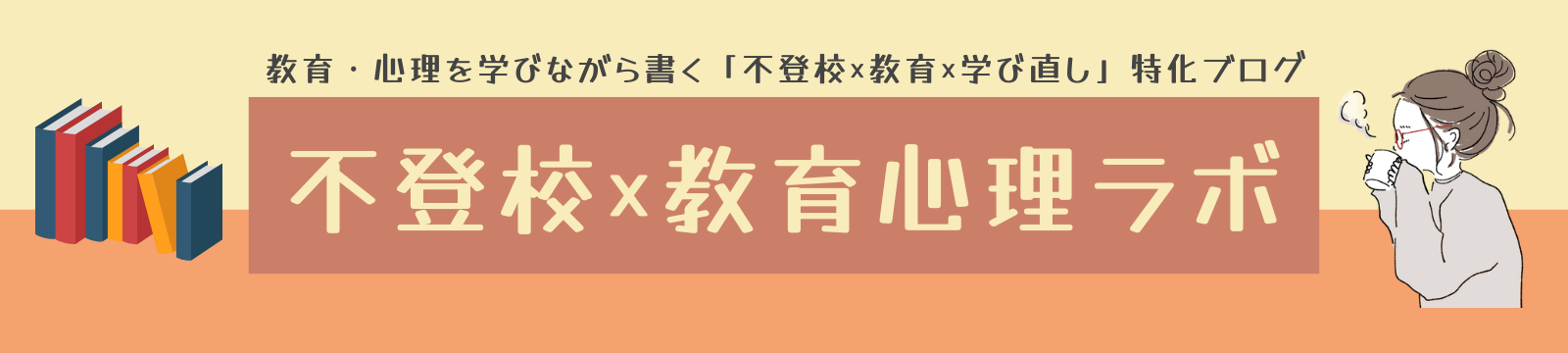
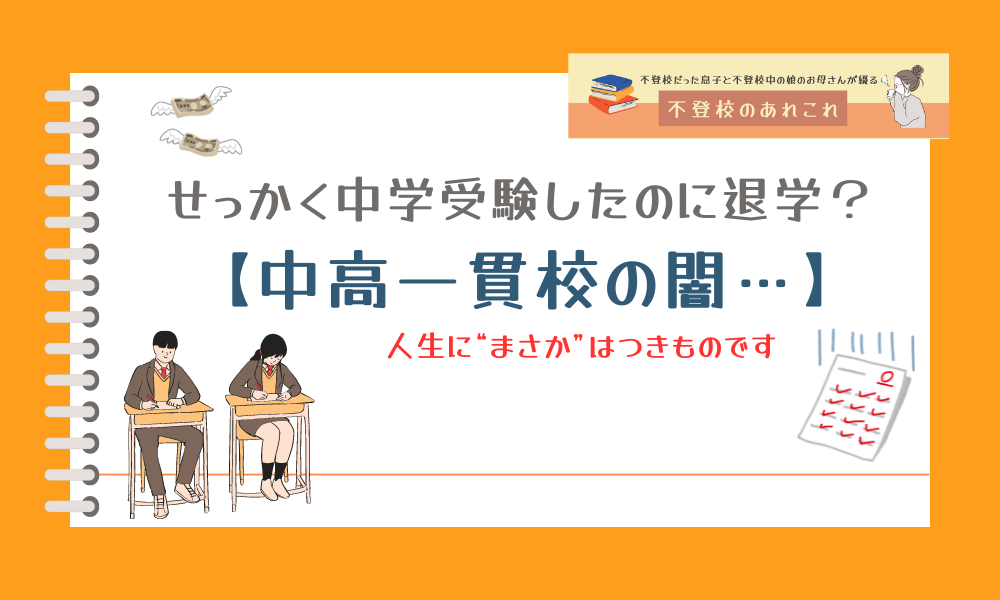
コメント