
どうしたらウチの子が不登校に…



このつらい気持ちはいつまで続くの?
「我が子が不登校になった」その出来事が起こると、多くの母親は胸を痛め涙が止まらなくなります。しかし、不登校は決して珍しいことではなく、今や多くのお母さんが同じ悩みを抱えています。
「子育てで何か間違えたのでは?」と自分を責めたり、終わりの見えない不登校に心が折れそうになったり…。でも、不登校の原因は1つではありません。
学校や友人関係、環境の変化、子ども自身の性格や心の状態など、さまざまな理由が複雑に絡み合っています。お母さんだけの責任ではないのです。



私の息子も不登校でした。娘は今も不登校継続中です。
母親にとってネガティブ要素が多い不登校問題。
だけど、子どもには子どもの可能性があり、素晴らしい未来を切り拓く力があるとわかったのも不登校になったからなんです。
この記事では、私の体験をもとに不登校の子どものお母さんが「つらい」と感じる理由と、その乗り越え方について詳しくお伝えします。
・元不登校の息子と不登校の娘のお母さん
・不登校をきっかけに家族関係を見直す
・息子現在留学生活を満喫中
・娘心の土台をコツコツ建設中
・不登校で闇の中にいる親御さんに「大丈夫!」を伝えたい
・どん底にいた私が今に至るまでの不登校のあれこれを発信中
・詳しいプロフィールはこちらから
不登校がつらい理由① | 自分をせめてしまうから
子どもが不登校になると、多くのお母さんが最初に感じるのは「自分のせいかもしれない」という強い自責の念です。
「もっとしっかりしていれば…」「もっと早く気づいてあげられたら…」と、後悔や自己嫌悪の気持ちで心がいっぱいになってしまう方も少なくありません。
しかし、子育てに完璧はありません。どんなに頑張っても、思い通りにいかないことや、つまずき、失敗は誰にでもあるものです。
それでも、わが子が学校に行けなくなった姿を目の当たりにすると、「自分の育て方が悪かったのでは」と自分を責めてしまうお母さんが多いのです。
不登校は「失敗」ではありません!
お子さんが不登校になったからといって、それは決して「子育ての失敗」ではありません。
「もっとこうしていれば…」「あの時、違う対応をしていれば…」と後悔する気持ちもよくわかります。でも、そのときそのときで、ベストを尽くしてきたはず!
不登校は、さまざまな要因が複雑に絡み合って起こるもので、決してお母さん一人の責任ではありません。お子さんの性格や学校・友人関係、環境の変化など、親がコントロールできない要素もたくさんあるのです。
「私のせい」と思い込まないで!
「子どもが不登校になったのは私のせい」と思い込んでしまうと、自分を責める気持ちがどんどん強くなり、心が疲れ切ってしまいます。
一生懸命子育てをしてきたお母さんほど、自分を責めてしまいがち。どうか一人で抱え込まないでくださいね。
子育ては、誰もが初めての経験です。迷いながら、悩みながら、手探りで進んでいくもの。
だから、自分を過剰に責める必要なんてないのです。今はまず、ご自身の心を大切にしてください。
不登校がつらい理由② | 子どもの将来が不安だから
お子さんが不登校になると、多くのお母さんが「このままで将来は大丈夫だろうか」と強い不安を抱きます。特に、不登校が長期化することで学業の遅れや進学への影響を心配する声は少なくありません。
進路や学力への不安
不登校が続くと「高校や大学に進学できないのでは?」「将来の選択肢が狭まるのでは?」と悩む方って多いですよね。しかし、実際には不登校を経験しても進学や就職の道は閉ざされていません。
文部科学省の調査によると、中学校で不登校だった人の8割以上が20歳時点で進学や就業をしているんですよ!
学習の遅れも、個別のペースで取り戻せるケースが多く、不登校の期間があっても進学や就職に大きな支障はないとされています。
確かに、不登校によって学習面での遅れが生じるのは事実です。しかし、それは人生の選択肢が狭まることと同義ではありません。むしろ、不登校を新たな可能性を発見するチャンスともとらえられます。
学校の枠にとらわれず、お子さんの個性や興味に合わせた多様な学び方を探求してみるのもいいかもしれません。
大切なのは、親が子どもの将来に前のめりにならないこと。お子さんのペースでじっくりと検討すればいいのです。お子さん自身に勉強する意欲が出てきたら、そのときはサポートしてあげてくださいね。



お子さんに活動する意欲がみられないときに勉強などを強制しても、それは逆効果になるだけですよ!
もし、お子さん自身が勉強の遅れを気にする様子でしたらオンライン学習や家庭教師ががおすすめです。
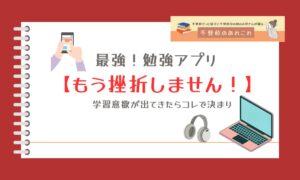
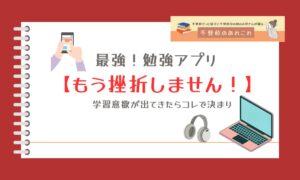
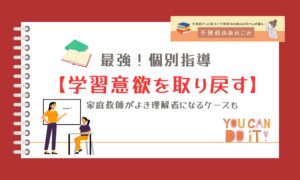
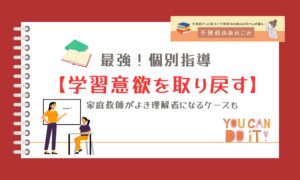
子どもの可能性が閉ざされる不安
進路の不安だけでなく、学校に通わないことで人間関係や社会性を身につける機会が減るのではと心配する方もいるでしょう。
長期の不登校によって、自己肯定感が下がったり社会とのつながりを持ちにくくなったりするリスクも指摘されているのは事実。
しかし、同時に「このままでは幸せになれないのでは…」と、過剰に不安を抱え込むのは危険です。
今は、フリースクールや通信制高校など多様な学びの場が増えています。大切なのは、お子さんのペースを尊重し、焦らず必要に応じて専門家や外部の力を借りながらサポートしていくことではないでしょうか?
不登校がつらい理由③ | まわりの目が怖いから
お子さんが不登校になると、多くのお母さんが「まわりの目が気になる」「何か言われるのでは」と強いプレッシャーや不安を感じます。
近所の方や親しいママ友から心配の言葉をかけられても、どこか責められているように受け取ってしまい、「私の子育てが悪かったのでは」と自分を責めてしまう方も少なくありません。
社会的なプレッシャー
日本では「子育ては母親の仕事」という固定観念が根強く、不登校の責任を母親一人が背負い込みやすい社会的な風潮があります。
そのため、親戚や近所の人、ママ友など周囲の目が気になり、「ちゃんと子育てしているの?」と非難されているように感じてしまう場合も。
実際に何か言われていなくても、無意識のうちに自分を責めてしまい、落ち込んでしまうケースが多いのです。
また、親戚やご近所、友人にお子さん不登校を打ち明けるのが怖くなり、必要以上に隠してしまったり、孤立感を深めてしまうお母さんもいます。
「うちの子だけが…」と感じてしまいがちですが、不登校は今や誰にでも起こりうる身近な問題です。
劣等感にさいなまれる
不登校のお子さんを持つ多くのお母さんは、「この子のために全てを捧げてきたのに、どうして…」という思いから、強い劣等感に苦しみがちです。
学校へ元気に通う他の子どもたちとわが子を比べてしまい、「自分の子育ては間違っていたのでは」と自信を失い、涙が止まらなくなる日もあるでしょう。
しかし、劣等感は決して「持ってはいけない感情」ではありません。誰しも他人と比べて落ち込むことはあります。しかし「ないもの」ばかりに目を向けてしまうと、劣等感はどんどん大きくなってしまいます。
どうか、お子さんやご自身の「今あるもの」「できていること」に意識を向けてみてください。
日々の中で小さな幸せや成長、笑顔など、当たり前のようで見落としがちな「良いところ」を探してみてくださいね!



劣等感に押しつぶされそうなときこそ、「ない」ではなく「ある」に目を向けてみてくださいね!
不登校がつらい理由④ | 仕事との両立が難しいから
お子さんが不登校になると、親は仕事と家庭の両立に大きな悩みを抱えます。特に母親は、子どものサポートのために仕事を休んだり早退したりする必要が生じ、職場への迷惑や自身のキャリアへの影響を心配するケースが多く見られます。
収入減と支出増のダブルパンチ
実際に、不登校をきっかけに世帯収入が減った家庭は3割にのぼり、約4割の家庭で支出が増えたという調査結果もあります。
働き方の変化としては「早退・遅刻が増えた」「休みがちになった」「退職した」といった声が多く、特にシングルマザーの場合は生活が大きく脅かされるのも珍しくありません。
また、フリースクールやカウンセリング、通院などの費用がかさみ、経済的な負担を重く感じている保護者は4割近くにのぼります。
子どもが家にいるため食費や光熱費が増える、給食費を払い続ける必要があるなど、細かな支出も積み重なります。
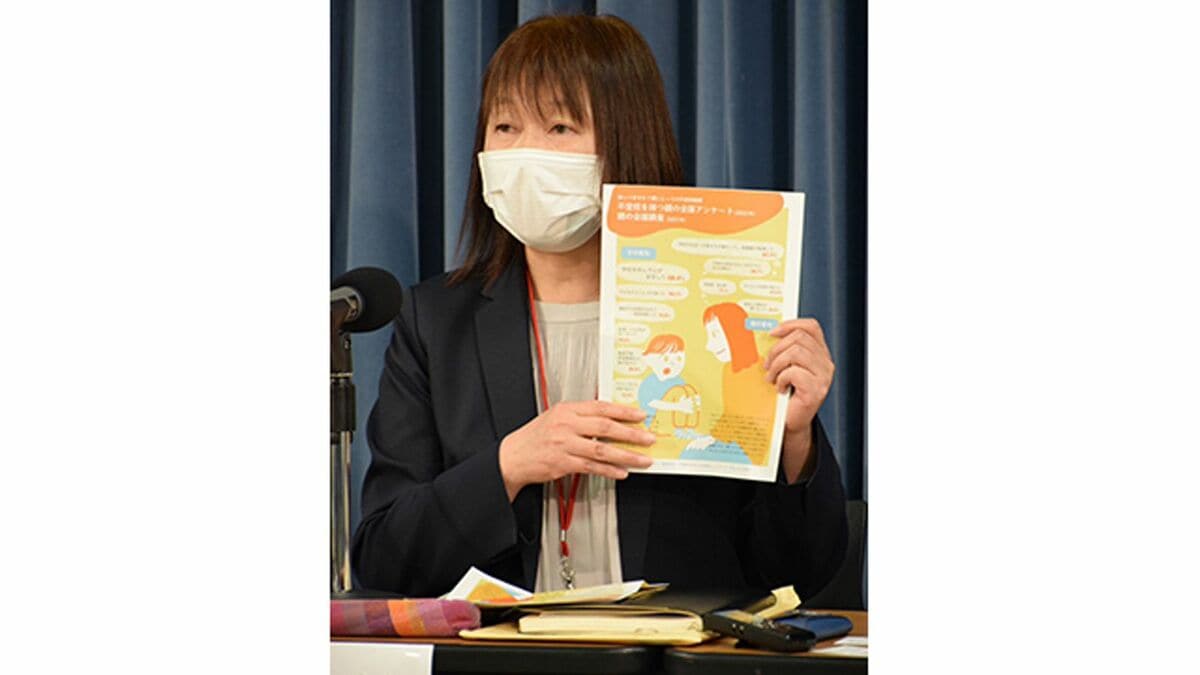
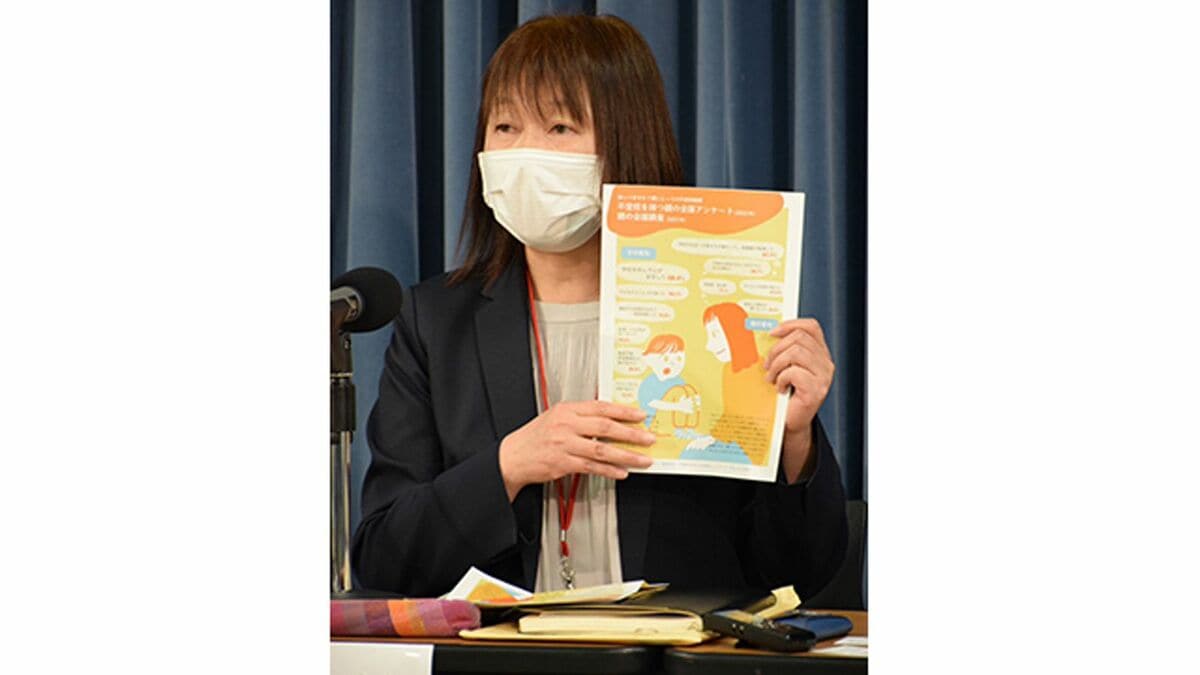
経済的な不安が家庭に与える影響
経済的な不安定さは、親のストレスや不安を増幅させ、子どもにも影響を及ぼしやすくなります。特にひとり親家庭では、国や自治体の支援制度を活用しながら、家計と子育ての両立を模索する必要があるでしょう。
参考:【日本財団ジャーナル】ひとり親家庭の貧困率は約5割。子育てに活用できる国や自治体の支援制度
不登校がつらい理由⑤ | メンタルが弱くなるから
お子さんが不登校になると、母親は強い孤独感や孤立無援の苦しみに直面します。最初は周囲の友人やママ友が心配してくれても、不登校が長引くにつれて徐々に距離を置かれ、「自分だけがこの状況にいる」と感じやすくなります。
孤独感からの脱出できない
周囲に同じ悩みを持つ人が少ないため、相談できる相手が見つからず、「誰もわかってくれない」と孤独を感じる母親は少なくありません。
「自分の育て方が悪かったのでは」「もっと何かできたのでは」と自分を責め、自己評価が下がり、無力感や自己否定に陥るケースも多いです。
社会的なプレッシャーや将来への不安も重なり、精神的な余裕がなくなりやすくなります。
メンタルの不調は親子関係にも影響
母親がストレスや不安、抑うつ状態に陥ると、家庭内の雰囲気が悪くなったり、親子のコミュニケーションが難しくなったりする場合もあります。子どもは、母親のの気持ちに敏感です。
母親の不安やイライラを感じ取ってしまい、さらに家庭全体のストレスが高まる悪循環に陥るケースもあるでしょう。
不登校の悩みは非常に大きな心理的負担となります。しかし「自分だけがつらい」と思い込まず、信頼できる人や専門家に相談することが大切。また、母親自身のケアやリフレッシュの時間を意識的に確保するのも、心の健康を保つために欠かせません。
ネガティブな思考から抜け出せないときは、以下の記事も参考にしてくださいね。
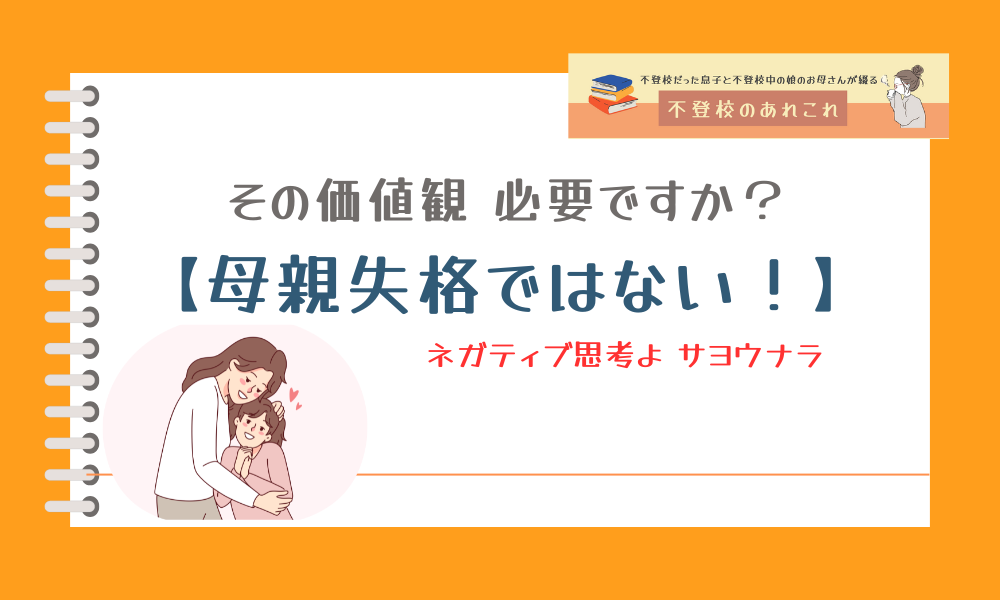
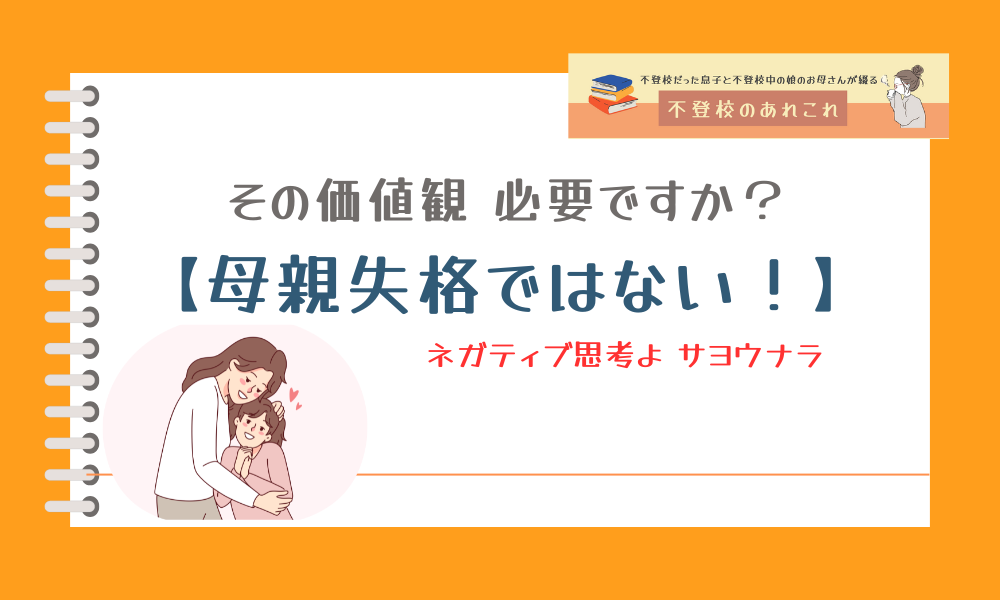
最後に | 不登校は「つらい」けれど、お母さん自身の心も大切に
子どもが不登校になって、私はたくさんのことを学びました。「子どもはきっと大丈夫」と信じていても、親である自分の心や体が疲れ切ってしまっては、その想いは支え続けられません。
今の時代、学校教育だけがすべてではありません。もちろん、学校に通うのも大切ですが、今の学校の仕組みや雰囲気が合わない子どもがいるのも事実です。
学校が好きな子は学校へ行けばいいし、そうでない子は他の選択肢を選んでもいい。これからの社会は、もっと多様な学び方や生き方が認められる時代です。
「学校へ行く・行かない」は、子どもの人生のすべてを決めるものではありません。学校に行かなくても、子どもは必ず成長し、未来を切り拓く力を持っています。



そして何より、お母さん自身の心と体を大切にしてくださいね。あなたが元気でいることが、お子さんにとって一番の安心につながりますから。
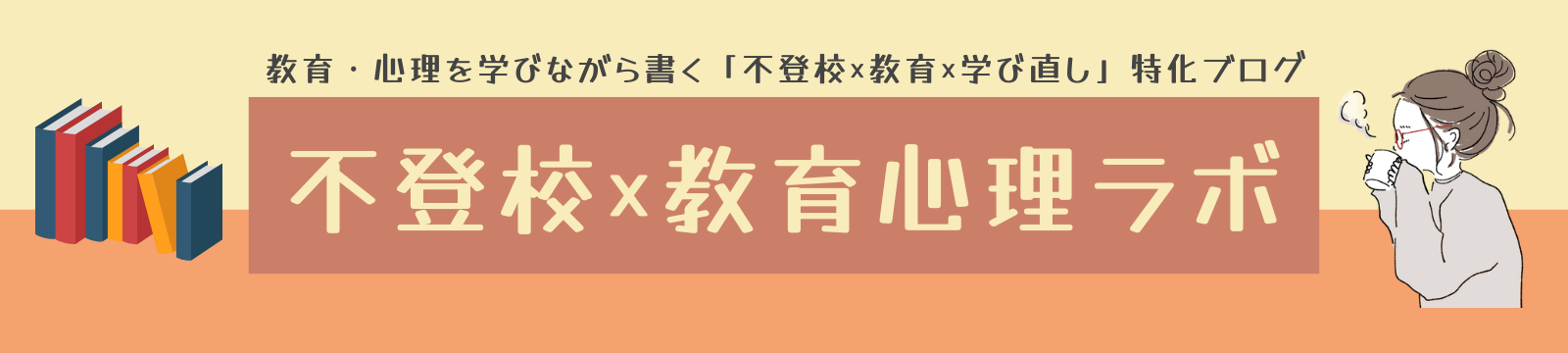
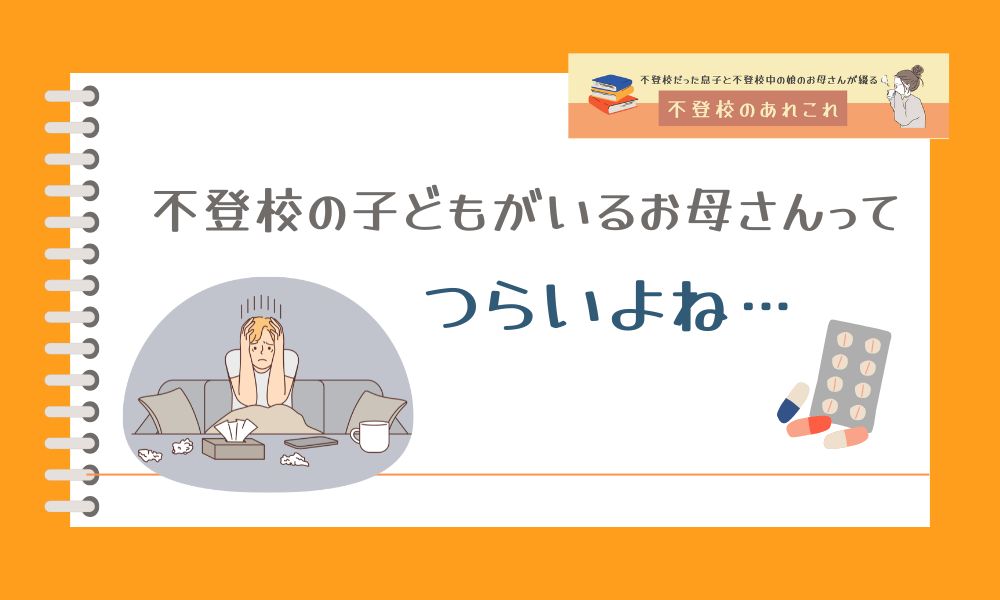
コメント